Perplexity AIとは?便利な活用シーンや他の生成AIツール、検索エンジンとの違いを徹底解説!!
Perplexity AIとは?便利な活用シーンや他の生成AIツール、検索エンジンとの違いを徹底解説!!
2024/12/15
2024/12/15
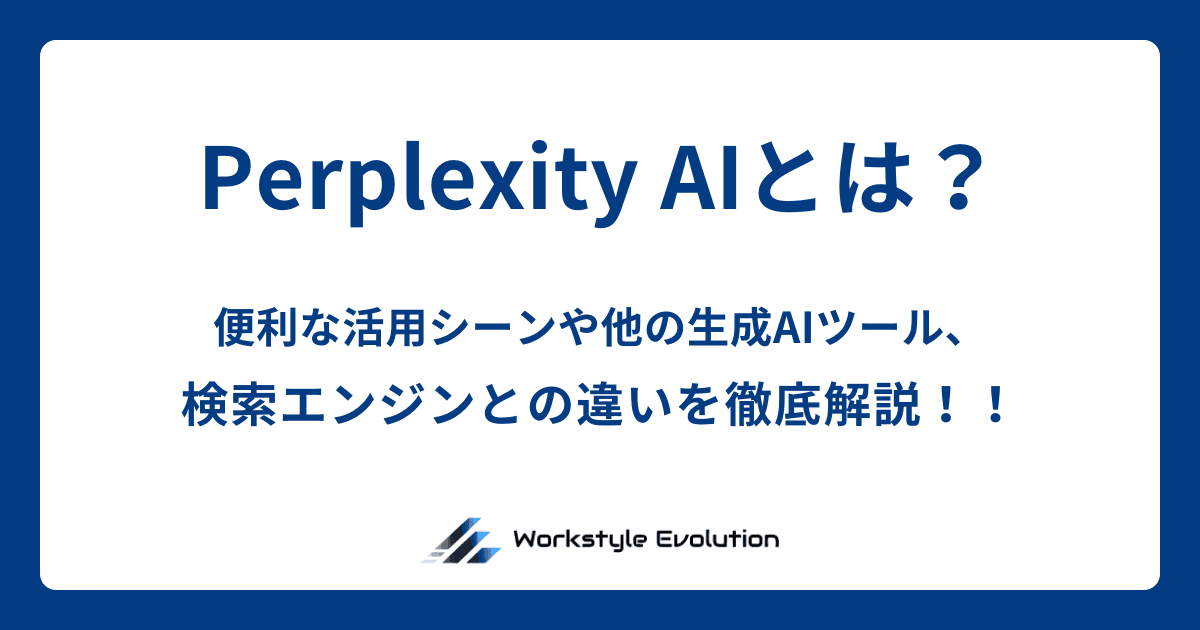
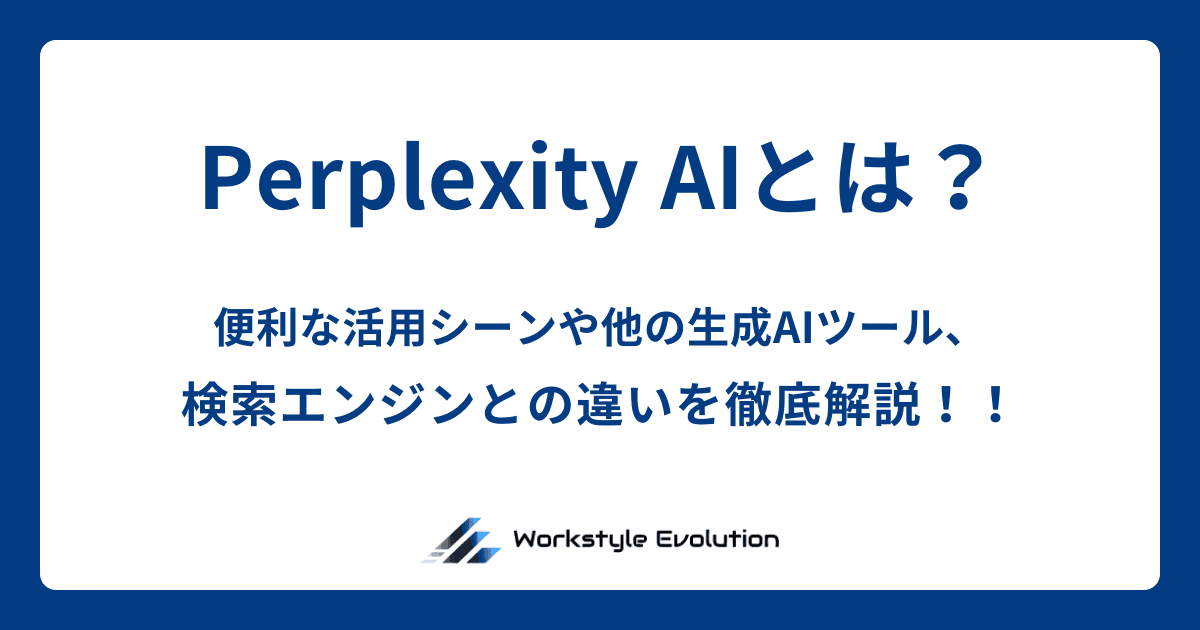
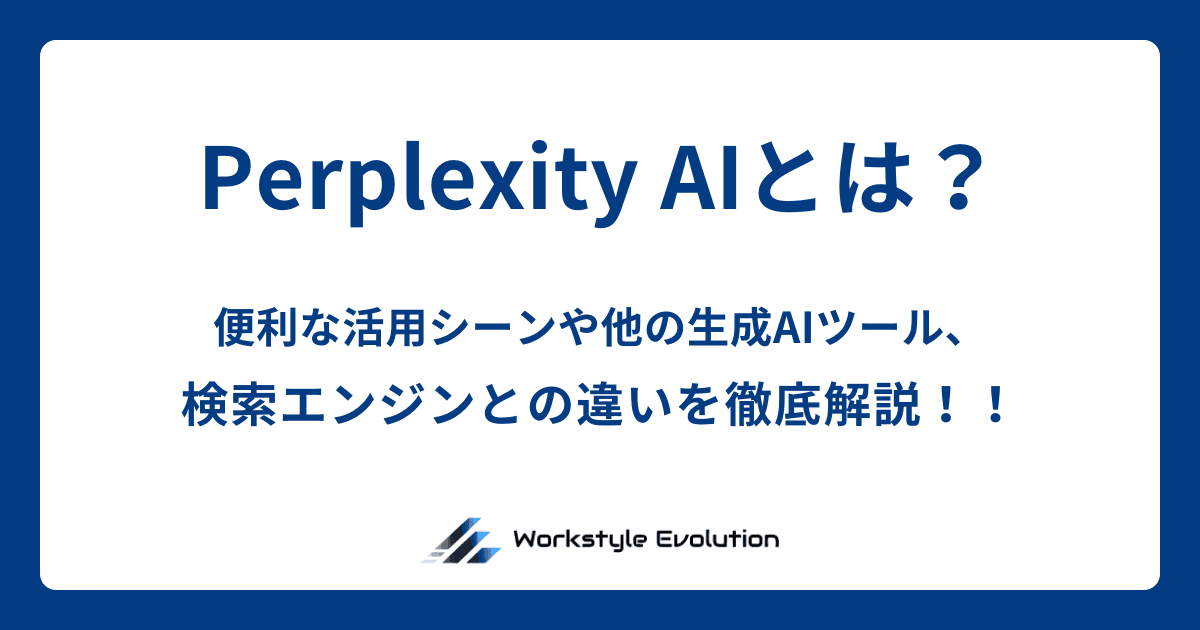
このコラムを要約すると…
Perplexity AIは、検索エンジンと生成AIの特徴を組み合わせた次世代の情報探索・分析ツールです。創業者はPerplexity AIのことを「WikipediaとChatGPTが授かったベイビー」と表現しており、これは同ツールの本質を端的に示しています。
主な特徴は以下の4点です:
回答力:ユーザーの質問意図を理解し、論理的な回答を導出
網羅力:インターネット上の最新情報をリアルタイムで収集
加工力:複雑なプロンプトに対応し、情報を高度に処理
引用力:情報源を明示し、回答の信頼性を担保
他のAIツールと比較すると、ChatGPTなどの汎用AIは情報処理に優れるものの最新情報の収集に制限があり、Gensparkなどの検索系AIは情報収集に特化する一方で情報加工の柔軟性に欠けます。Perplexity AIはこれらの機能をバランスよく備え、特にビジネスシーンでの競合分析や市場調査、学術研究での情報収集など、幅広い場面で活用できます。ただし、AIツールは日々アップデートしているため、適宜目的に応じて適切なツールを選択することが重要です。
このコラムを要約すると…
Perplexity AIは、検索エンジンと生成AIの特徴を組み合わせた次世代の情報探索・分析ツールです。創業者はPerplexity AIのことを「WikipediaとChatGPTが授かったベイビー」と表現しており、これは同ツールの本質を端的に示しています。
主な特徴は以下の4点です:
回答力:ユーザーの質問意図を理解し、論理的な回答を導出
網羅力:インターネット上の最新情報をリアルタイムで収集
加工力:複雑なプロンプトに対応し、情報を高度に処理
引用力:情報源を明示し、回答の信頼性を担保
他のAIツールと比較すると、ChatGPTなどの汎用AIは情報処理に優れるものの最新情報の収集に制限があり、Gensparkなどの検索系AIは情報収集に特化する一方で情報加工の柔軟性に欠けます。Perplexity AIはこれらの機能をバランスよく備え、特にビジネスシーンでの競合分析や市場調査、学術研究での情報収集など、幅広い場面で活用できます。ただし、AIツールは日々アップデートしているため、適宜目的に応じて適切なツールを選択することが重要です。
目次
目次
OpenAI社が、2022年11月にChatGPTをリリースして以降、生成AI技術は急速な進化を遂げています。2024年現在、世界には数千以上の生成AI関連ツールが存在するとも言われ、その用途や機能は多岐にわたります。検索、文章生成、画像生成、音声合成など、様々な分野で革新的なAIツールが次々と登場しています。
そうした中で、Perplexity AIは特に注目を集めているツールの一つです。単なる検索ツールや生成AIの枠を超えて、高度な情報検索能力と論理的な情報処理能力を兼ね備えた次世代の情報探索・分析プラットフォームとして、ビジネスユーザーから研究者、学生まで、幅広い層から高い評価を得ています。

従来の検索エンジンは膨大な情報の中からキーワードに関連する情報を探し出すことに長けており、ChatGPTに代表される生成AIは与えられた情報を理解し加工する能力に優れています。Perplexity AIはこれら二つの特徴を効果的に組み合わせることで、ユーザーが本当に必要とする情報を、より正確に、より使いやすい形で提供することを可能にしました。
本コラムでは、Perplexity AIの基本的な特徴や機能を詳しく解説するとともに、ビジネスや日常生活における具体的な活用シーンをご紹介します。さらに、ChatGPTをはじめとする他の生成AIツールと比較した際の違いについても、実例を交えながら、わかりやすく説明していきます。
OpenAI社が、2022年11月にChatGPTをリリースして以降、生成AI技術は急速な進化を遂げています。2024年現在、世界には数千以上の生成AI関連ツールが存在するとも言われ、その用途や機能は多岐にわたります。検索、文章生成、画像生成、音声合成など、様々な分野で革新的なAIツールが次々と登場しています。
そうした中で、Perplexity AIは特に注目を集めているツールの一つです。単なる検索ツールや生成AIの枠を超えて、高度な情報検索能力と論理的な情報処理能力を兼ね備えた次世代の情報探索・分析プラットフォームとして、ビジネスユーザーから研究者、学生まで、幅広い層から高い評価を得ています。

従来の検索エンジンは膨大な情報の中からキーワードに関連する情報を探し出すことに長けており、ChatGPTに代表される生成AIは与えられた情報を理解し加工する能力に優れています。Perplexity AIはこれら二つの特徴を効果的に組み合わせることで、ユーザーが本当に必要とする情報を、より正確に、より使いやすい形で提供することを可能にしました。
本コラムでは、Perplexity AIの基本的な特徴や機能を詳しく解説するとともに、ビジネスや日常生活における具体的な活用シーンをご紹介します。さらに、ChatGPTをはじめとする他の生成AIツールと比較した際の違いについても、実例を交えながら、わかりやすく説明していきます。
Perplexity AIとは?
Perplexity AIは、従来の検索エンジンの枠を超えた次世代の情報探索・分析ツールです。一般に日本では「検索系の生成AIツールの一種」と認識されることが多いように思えますが、Perplexity AIの本質は情報を集約して整理する「論理的な思考力」です。たとえば、古典的な検索エンジンでは、特定のキーワードに基づく一問一答型の検索が一般的でした。しかしPerplexity AIはその検索過程において高度なAIを組み合わせており、ユーザーの意図を理解した上で特定のタスクを処理することで、より適切な情報提供を行うことができます。
Perplexity AIの創業者であるアラヴィンド・スリニヴァス氏は、Perplexityのことを「ウィキペディアとChatGPTが授かったベイビー」と表現しています。この発言は、ユーザーの質問の意図を適切汲み取り、ネット上から網羅的に情報を収集し、その情報を適切に整理・分解・加工し、証跡を追える引用リソースを添えた状態でユーザーに提示するという、流暢でエレガントなPerplexity AIの一連の機能を意識したものだと考えられます。

強力な生成AIの機能を組み込んだPerplexity AIがユーザーに提供することができる「価値」は、大まかに以下の4つにまとめられると考えられます。
1.回答力: ユーザーの質問を理解し、集めた情報から回答を論理的に導く能力。
2.網羅力: ネット上の情報を迅速に、リアルタイムで収集し、回答を生成する能力。
3.加工力: 高度なプロンプトを理解し情報を処理、分解、整理する能力。
4.引用力: 生成した回答の根拠となる情報源やリソースを明示する能力。

それぞれの価値について詳しく見ていきましょう。
Perplexity AIとは?
Perplexity AIは、従来の検索エンジンの枠を超えた次世代の情報探索・分析ツールです。一般に日本では「検索系の生成AIツールの一種」と認識されることが多いように思えますが、Perplexity AIの本質は情報を集約して整理する「論理的な思考力」です。たとえば、古典的な検索エンジンでは、特定のキーワードに基づく一問一答型の検索が一般的でした。しかしPerplexity AIはその検索過程において高度なAIを組み合わせており、ユーザーの意図を理解した上で特定のタスクを処理することで、より適切な情報提供を行うことができます。
Perplexity AIの創業者であるアラヴィンド・スリニヴァス氏は、Perplexityのことを「ウィキペディアとChatGPTが授かったベイビー」と表現しています。この発言は、ユーザーの質問の意図を適切汲み取り、ネット上から網羅的に情報を収集し、その情報を適切に整理・分解・加工し、証跡を追える引用リソースを添えた状態でユーザーに提示するという、流暢でエレガントなPerplexity AIの一連の機能を意識したものだと考えられます。

強力な生成AIの機能を組み込んだPerplexity AIがユーザーに提供することができる「価値」は、大まかに以下の4つにまとめられると考えられます。
1.回答力: ユーザーの質問を理解し、集めた情報から回答を論理的に導く能力。
2.網羅力: ネット上の情報を迅速に、リアルタイムで収集し、回答を生成する能力。
3.加工力: 高度なプロンプトを理解し情報を処理、分解、整理する能力。
4.引用力: 生成した回答の根拠となる情報源やリソースを明示する能力。

それぞれの価値について詳しく見ていきましょう。
回答力:
一昔前よりGoogle等の検索エンジンの回答能力が高度化していることは、多くの方がご存知かと思います。例えば私は北海道に住んでいる関係で、最近興味があって「日本で最北端の神社」と最近Googleで検索を行いました(下図)。するとGoogleは、単にユーザーが入力したキーワードが多く含まれるWebサイトを上位表示するのではなく、インターネット上で収集した情報をもとに「最北端の神社」=「北門神社」だとまず類推した上で、北門神社のWebサイトや観光系のブログ記事を優先的に表示してくれました。

では次に「北海道で車のワイパーを立てた方がよい気温」とGoogleで検索してみましょう(道外の方へ補足いたしますと、北海道の冬はワイパーを立てて駐車しないとゴムとガラスが張り付いて故障の原因になります)。残念ながらGoogleは「ワイパー」や「北海道」といった個々のキーワードが多く含まれたWebサイトを表示するに留まり、具体的な気温は回答できませんでした(下図)。先ほどの北門神社の例と異なり、ワイパーを立てた方がよい気温=〇〇度という直接的な回答が含まれたWebサイトが枯渇しているため、質問の意図を反映した回答をうまく抽出することができないのです。

それではPerplexity AIで同様の質問をしてみましょう。同様の検索キーワードを入力すると、インターネット上で集めた情報から「気温が0度以下になるとワイパーを立てることが推奨される」という具体的な気温を類推して回答するだけでなく、天気予報を踏まえて「ワイパーを立てた方がよい」日を提示してくれました(下図)。
これは北海道で車を持ち始めたばかりの自分にとって、非常に有益な情報です。もちろんこのPerplexity AIも完璧な回答を提供してくれる訳ではありません。しかし、少なくとも「ちょっと聞いていい?」と知り合いに質問する時と同じぐらいの精度で、気の利いた回答を提供してくれる点は大きなメリットだと考えられます。

このように、Perplexity AIの強みは単にユーザーの入力結果に沿ったWebサイトを表示するだけでなく、ユーザーが真に求めている情報を類推し、集められた情報からその具体的な回答を論理的に導くことができる点であるといえます。
回答力:
一昔前よりGoogle等の検索エンジンの回答能力が高度化していることは、多くの方がご存知かと思います。例えば私は北海道に住んでいる関係で、最近興味があって「日本で最北端の神社」と最近Googleで検索を行いました(下図)。するとGoogleは、単にユーザーが入力したキーワードが多く含まれるWebサイトを上位表示するのではなく、インターネット上で収集した情報をもとに「最北端の神社」=「北門神社」だとまず類推した上で、北門神社のWebサイトや観光系のブログ記事を優先的に表示してくれました。

では次に「北海道で車のワイパーを立てた方がよい気温」とGoogleで検索してみましょう(道外の方へ補足いたしますと、北海道の冬はワイパーを立てて駐車しないとゴムとガラスが張り付いて故障の原因になります)。残念ながらGoogleは「ワイパー」や「北海道」といった個々のキーワードが多く含まれたWebサイトを表示するに留まり、具体的な気温は回答できませんでした(下図)。先ほどの北門神社の例と異なり、ワイパーを立てた方がよい気温=〇〇度という直接的な回答が含まれたWebサイトが枯渇しているため、質問の意図を反映した回答をうまく抽出することができないのです。

それではPerplexity AIで同様の質問をしてみましょう。同様の検索キーワードを入力すると、インターネット上で集めた情報から「気温が0度以下になるとワイパーを立てることが推奨される」という具体的な気温を類推して回答するだけでなく、天気予報を踏まえて「ワイパーを立てた方がよい」日を提示してくれました(下図)。
これは北海道で車を持ち始めたばかりの自分にとって、非常に有益な情報です。もちろんこのPerplexity AIも完璧な回答を提供してくれる訳ではありません。しかし、少なくとも「ちょっと聞いていい?」と知り合いに質問する時と同じぐらいの精度で、気の利いた回答を提供してくれる点は大きなメリットだと考えられます。

このように、Perplexity AIの強みは単にユーザーの入力結果に沿ったWebサイトを表示するだけでなく、ユーザーが真に求めている情報を類推し、集められた情報からその具体的な回答を論理的に導くことができる点であるといえます。
網羅力:
Perplexity AIの大きな特徴の一つは、インターネット上の情報をリアルタイムで収集・分析できる点です。特に重要なのは情報の即時性です。例えば、同じ生成AIツールであるAnthropic社のClaudeが数か月前の学習データに基づいて回答するのに対し、Perplexity AIは最新のウェブ情報を基に回答を生成できます。
例えば本記事を執筆した前日(2024/11/24)、残念ながら野球の侍ジャパンは「プレミア12」の決勝戦で台湾に負けてしまいました。この決勝戦の経緯や背景をClaudeに聞いても「2024年4月の時点での知識に基づいて、その後に行われた試合の詳細について正確な情報をお伝えすることはできません。」と回答されるにとどまります。一方でPerplexity AIは最新のネット上の情報を網羅的に検索し、概要や試合展開、社会的な影響度をわかりやすくまとめて示してくれます(下図)。

このようにユーザーが知りたいと考えるポイントに沿った巨視的な情報を、質問してから僅か10秒足らずで作成してくれる驚異的なスピードこそ、Perplexity AIの大きな強みです。このリアルタイム性というPerplexity AIの特徴は、ニュースや時事問題に関する質問、最新のトレンドや製品情報の調査などにおいて特に威力を発揮します。
なおOpen AI社も2024年10月にChatGPT searchをリリースし、ChatGPT上の回答にインターネット上の情報をリアルタイムで収集、回答に反映させる機能を実装しました。しかし回答そのものが若干言葉足らずな感は否めず(下図)、本コラムの執筆時点において情報の網羅力という面ではPerplexity AIに優位性があると考えられます。

網羅力:
Perplexity AIの大きな特徴の一つは、インターネット上の情報をリアルタイムで収集・分析できる点です。特に重要なのは情報の即時性です。例えば、同じ生成AIツールであるAnthropic社のClaudeが数か月前の学習データに基づいて回答するのに対し、Perplexity AIは最新のウェブ情報を基に回答を生成できます。
例えば本記事を執筆した前日(2024/11/24)、残念ながら野球の侍ジャパンは「プレミア12」の決勝戦で台湾に負けてしまいました。この決勝戦の経緯や背景をClaudeに聞いても「2024年4月の時点での知識に基づいて、その後に行われた試合の詳細について正確な情報をお伝えすることはできません。」と回答されるにとどまります。一方でPerplexity AIは最新のネット上の情報を網羅的に検索し、概要や試合展開、社会的な影響度をわかりやすくまとめて示してくれます(下図)。

このようにユーザーが知りたいと考えるポイントに沿った巨視的な情報を、質問してから僅か10秒足らずで作成してくれる驚異的なスピードこそ、Perplexity AIの大きな強みです。このリアルタイム性というPerplexity AIの特徴は、ニュースや時事問題に関する質問、最新のトレンドや製品情報の調査などにおいて特に威力を発揮します。
なおOpen AI社も2024年10月にChatGPT searchをリリースし、ChatGPT上の回答にインターネット上の情報をリアルタイムで収集、回答に反映させる機能を実装しました。しかし回答そのものが若干言葉足らずな感は否めず(下図)、本コラムの執筆時点において情報の網羅力という面ではPerplexity AIに優位性があると考えられます。

加工力:
現在私は生成AIコンサルタントとして多くの企業や組織の研修や生成AI導入支援を行っていますが、「検索系AI」というPerplexity AIの紹介文は、十分にそのポテンシャルを表現できていないと感じています。この点を、類似する検索系生成AIツールとして取り上げられることが多いGensparkとの比較を通じて説明していきたいと思います。
Perplexity AIがシンプルで迅速な回答結果を示すのに対して、Gensparkは参照元となる情報量の多さや多角的な視点での情報収集に優れており、この特徴から一部界隈では「GensparkはPerplexity AIを超えた」と語られる場面も増えています。実際に先の例である「北海道でワイパーを立てた方がよい気温」をGensparkに投入してみましょう。回答の生成スピードはPerplexity AIに劣るものの、情報の網羅性や生成能力そのものは、確かに負けない、むしろGensparkの方が優れている面もあるように見受けられます(下図)。

しかしPerplexity AIの神髄は単なる「検索結果をまとめる力」に留まりません。高度で複雑なプロンプトを通じて検索結果の情報を整理・加工する力にこそ、その特徴があると私は考えています。以下はWorkstyle Evolution社が2024年11月に出版した「Perplexity 最強のAI検索術」にも記載されている、法人営業担当が顧客企業を所定のチェックリストに沿って網羅的に調査するプロンプトの抜粋です(全文は購読者の方には特典として無料で配布しております)。
あなたはWorkstyle Evolutionという生成AIコンサル会社に務める、網羅的なチェックが得意な優秀な営業マン兼生成AIコンサルタントです。私は同じ会社に勤める新人営業です。
ある企業を新規顧客として、いまから生成AI研修の提案に向けて企業情報を網羅的にチェックしたいと思っています。
以下のチェックシートに沿ってWeb上の情報を確認し、その結果を記載してください。
重要:検索結果は急がないので、なるべく長文かつ網羅的に記載してください。重要:予測系AIなど、生成AIではないAI領域に関する検索ではなく、あくまで生成AIにチェック領域を絞ってください。
# 対象企業株式会社メンバーズ
# 事前調査すべき内容
## 事業内容###1. 対象企業の事業ポートフォリオは何か?どの事業が主な収益源か?###2. 最近はじめられた新規事業、新規サービスはあるか?戦略上どのような位置づけか?###3. 企業の人数や規模は?組織別に…(以下略)
ビジネス=営業活動での利用ということもあり、それなりに精度が高い情報を入手したいため、プロンプトには「長文かつ網羅的に…」という要件を追記しました。このプロンプトをGensparkとPerplexity AIにそれぞれ投入してみましょう。明確な差はまず情報の生成スピードで生じます。Perplexity AIでも全ての回答が表示されるまでは若干の時間を要しましたが、Gensparkは体感値で10倍以上の時間を要しました(また余りに時間が掛かるので、十数個のチェック項目のうち一部は作成を諦めました)。生成されたアウトプットの質についても、Perplexity AIではGensparkよりも詳細で洞察力の高い回答が導かれているように見受けられます(下図)。
■Gensparkによるアウトプット

■Perplexityによるアウトプット

Perplexity AIとGensparkの差は「あなたは網羅的なチェックが得意な…」というタスクの背景を指示としてどれだけ理解し、情報処理に活かせているかという点に表れています。なおPerplexity AIにはGPT-4やClaude-3.5 Sonnetといった最新のLLM(大規模言語モデル)が組み込まれており、ユーザーの嗜好に合わせてモデルを変更することが可能です。この機能により、ネット上の情報にとどまらず、ユーザーが入力した社内情報も含めて高度なタスクを実行させることが可能となります。
特に複雑なビジネスの場面になるほど、情報の取捨選択が一般的な「検索」だけで完結するシーンは多くありません。ある程度複雑で、高度なプロンプトを投入しても理解できるだけの地頭を備えている点が、他の検索系生成AIツールとPerplexity AIの大きな違いです。
加工力:
現在私は生成AIコンサルタントとして多くの企業や組織の研修や生成AI導入支援を行っていますが、「検索系AI」というPerplexity AIの紹介文は、十分にそのポテンシャルを表現できていないと感じています。この点を、類似する検索系生成AIツールとして取り上げられることが多いGensparkとの比較を通じて説明していきたいと思います。
Perplexity AIがシンプルで迅速な回答結果を示すのに対して、Gensparkは参照元となる情報量の多さや多角的な視点での情報収集に優れており、この特徴から一部界隈では「GensparkはPerplexity AIを超えた」と語られる場面も増えています。実際に先の例である「北海道でワイパーを立てた方がよい気温」をGensparkに投入してみましょう。回答の生成スピードはPerplexity AIに劣るものの、情報の網羅性や生成能力そのものは、確かに負けない、むしろGensparkの方が優れている面もあるように見受けられます(下図)。

しかしPerplexity AIの神髄は単なる「検索結果をまとめる力」に留まりません。高度で複雑なプロンプトを通じて検索結果の情報を整理・加工する力にこそ、その特徴があると私は考えています。以下はWorkstyle Evolution社が2024年11月に出版した「Perplexity 最強のAI検索術」にも記載されている、法人営業担当が顧客企業を所定のチェックリストに沿って網羅的に調査するプロンプトの抜粋です(全文は購読者の方には特典として無料で配布しております)。
あなたはWorkstyle Evolutionという生成AIコンサル会社に務める、網羅的なチェックが得意な優秀な営業マン兼生成AIコンサルタントです。私は同じ会社に勤める新人営業です。
ある企業を新規顧客として、いまから生成AI研修の提案に向けて企業情報を網羅的にチェックしたいと思っています。
以下のチェックシートに沿ってWeb上の情報を確認し、その結果を記載してください。
重要:検索結果は急がないので、なるべく長文かつ網羅的に記載してください。重要:予測系AIなど、生成AIではないAI領域に関する検索ではなく、あくまで生成AIにチェック領域を絞ってください。
# 対象企業株式会社メンバーズ
# 事前調査すべき内容
## 事業内容###1. 対象企業の事業ポートフォリオは何か?どの事業が主な収益源か?###2. 最近はじめられた新規事業、新規サービスはあるか?戦略上どのような位置づけか?###3. 企業の人数や規模は?組織別に…(以下略)
ビジネス=営業活動での利用ということもあり、それなりに精度が高い情報を入手したいため、プロンプトには「長文かつ網羅的に…」という要件を追記しました。このプロンプトをGensparkとPerplexity AIにそれぞれ投入してみましょう。明確な差はまず情報の生成スピードで生じます。Perplexity AIでも全ての回答が表示されるまでは若干の時間を要しましたが、Gensparkは体感値で10倍以上の時間を要しました(また余りに時間が掛かるので、十数個のチェック項目のうち一部は作成を諦めました)。生成されたアウトプットの質についても、Perplexity AIではGensparkよりも詳細で洞察力の高い回答が導かれているように見受けられます(下図)。
■Gensparkによるアウトプット

■Perplexityによるアウトプット

Perplexity AIとGensparkの差は「あなたは網羅的なチェックが得意な…」というタスクの背景を指示としてどれだけ理解し、情報処理に活かせているかという点に表れています。なおPerplexity AIにはGPT-4やClaude-3.5 Sonnetといった最新のLLM(大規模言語モデル)が組み込まれており、ユーザーの嗜好に合わせてモデルを変更することが可能です。この機能により、ネット上の情報にとどまらず、ユーザーが入力した社内情報も含めて高度なタスクを実行させることが可能となります。
特に複雑なビジネスの場面になるほど、情報の取捨選択が一般的な「検索」だけで完結するシーンは多くありません。ある程度複雑で、高度なプロンプトを投入しても理解できるだけの地頭を備えている点が、他の検索系生成AIツールとPerplexity AIの大きな違いです。
引用力:
生成AIを利用する際の最大の課題の一つとして、ハルシネーション(幻覚)とよばれる「嘘」や「誤謬」が表示されてしまうことが挙げられます。これは生成AIが学習データを基に「もっともらしい」回答を作り出してしまうことに起因する問題です。この課題に対し、Perplexity AIは表示結果の情報元となるWebサイトやリソースを明示的に提示し、ユーザーが元の情報に遡って確認することを可能にしています。これにより、ハルシネーションが発生した場合の検知を容易にしています。
この引用機能は、特にレポートや論文といった客観性が求められるアウトプットを作成する際の補助ツールとして生成AIを利用する場合においては特に重要です。学術研究やリサーチ資料においては査読を通じて致命的な誤謬を防ぐための「追跡可能性(トレーサビリティ)」が重要視されています。情報の出典を明確に示すことは、アウトプットの信頼性と価値を大きく高めることにつながります。
例えば「生成AIが人間の創造性に与える影響について、ポジティブ派とネガティブ派の意見を、なるべく多くの専門家や有識者の主張を抑えた上で、できる限り網羅的に教えてください。」という複雑な質問をした場合、Perplexity AIは各主張の出典を明確に示しながら、賛成派と反対派の議論の背景にある主要な論点について、専門家の見解を引用しながら解説してくれます(下図)。

さらに、Perplexity AIは引用機能に関して「信頼度の高いドメインからの情報のみを参照する」「特定の時期の情報のみを参照する」「学術論文や公式文書などの特定タイプの情報源に限定する」といった高度なカスタマイズ性も提供しています。これらの機能を通じて、ユーザーは利用用途に従って適切な範囲で情報を収集し、信頼性を効果的に高めることができます。例えば、学術研究においては査読付き論文のみを参照する、ビジネスレポートでは直近1年以内の情報に限定して情報収集を行うといった個別の文脈に沿った使い方が可能です。
このような充実した引用機能は、Perplexity AIが単なる検索ツールではなく、人間の活動を支える知的プラットフォームとしての価値を持つことを示しています。特に、正確性と信頼性が重要視される発信において、Perplexity AIの引用機能は他のAIツールと一線を画する強みを有すると言えるでしょう。
Perplexity AIの具体的な活用方法や利用シーンは?
今まで見た通りPerplexity AIは「回答力: 質問意図を理解し、回答を論理的に導く力」「網羅力: 情報を迅速に、リアルタイムに収集する力」「加工力: プロンプトを理解し、情報を分解・整理する力」「引用力: 生成した回答の根拠を明示する力」という4つの優れた特徴を有します。これらの特徴を活かした具体的な活用方法を、以下の場面で考えてみたいと思います。
引用力:
生成AIを利用する際の最大の課題の一つとして、ハルシネーション(幻覚)とよばれる「嘘」や「誤謬」が表示されてしまうことが挙げられます。これは生成AIが学習データを基に「もっともらしい」回答を作り出してしまうことに起因する問題です。この課題に対し、Perplexity AIは表示結果の情報元となるWebサイトやリソースを明示的に提示し、ユーザーが元の情報に遡って確認することを可能にしています。これにより、ハルシネーションが発生した場合の検知を容易にしています。
この引用機能は、特にレポートや論文といった客観性が求められるアウトプットを作成する際の補助ツールとして生成AIを利用する場合においては特に重要です。学術研究やリサーチ資料においては査読を通じて致命的な誤謬を防ぐための「追跡可能性(トレーサビリティ)」が重要視されています。情報の出典を明確に示すことは、アウトプットの信頼性と価値を大きく高めることにつながります。
例えば「生成AIが人間の創造性に与える影響について、ポジティブ派とネガティブ派の意見を、なるべく多くの専門家や有識者の主張を抑えた上で、できる限り網羅的に教えてください。」という複雑な質問をした場合、Perplexity AIは各主張の出典を明確に示しながら、賛成派と反対派の議論の背景にある主要な論点について、専門家の見解を引用しながら解説してくれます(下図)。

さらに、Perplexity AIは引用機能に関して「信頼度の高いドメインからの情報のみを参照する」「特定の時期の情報のみを参照する」「学術論文や公式文書などの特定タイプの情報源に限定する」といった高度なカスタマイズ性も提供しています。これらの機能を通じて、ユーザーは利用用途に従って適切な範囲で情報を収集し、信頼性を効果的に高めることができます。例えば、学術研究においては査読付き論文のみを参照する、ビジネスレポートでは直近1年以内の情報に限定して情報収集を行うといった個別の文脈に沿った使い方が可能です。
このような充実した引用機能は、Perplexity AIが単なる検索ツールではなく、人間の活動を支える知的プラットフォームとしての価値を持つことを示しています。特に、正確性と信頼性が重要視される発信において、Perplexity AIの引用機能は他のAIツールと一線を画する強みを有すると言えるでしょう。
Perplexity AIの具体的な活用方法や利用シーンは?
今まで見た通りPerplexity AIは「回答力: 質問意図を理解し、回答を論理的に導く力」「網羅力: 情報を迅速に、リアルタイムに収集する力」「加工力: プロンプトを理解し、情報を分解・整理する力」「引用力: 生成した回答の根拠を明示する力」という4つの優れた特徴を有します。これらの特徴を活かした具体的な活用方法を、以下の場面で考えてみたいと思います。
Perplexity AIと他の生成AIツール、検索エンジンとの違いは?
これまで、いくつかの生成AIツールとの比較を通じてPerplexity AIの特徴をご紹介するとともに、Perplexity AIが利用できる具体的なシーンについても言及してまいりました。生成AIの進化はすさまじく、本コラム執筆時点(2024/11/24)でも様々な生成AIツールが世界中でリリースされています。
本コラムに登場したさまざまな生成AIツールや検索エンジンとPerplexity AIの違いを一枚の図に表したものがこちらです。横軸の情報検索力はインターネット上の情報を収集する量(網羅性)とスピードを、縦軸の情報処理力は検索結果を加工、分類、または発展させる能力を表しています。

この図から見て取れる特徴的な点として、Perplexity AIは情報検索力と情報処理力の両面でバランスの取れた性能を発揮していることが挙げられます。従来の検索エンジンと比較すると、情報検索においては同等以上の能力を持ちながら、情報処理の面で大きな優位性を示しています。
一方、ChatGPTやClaudeなどの汎用生成AIツールと比較すると、これらは情報処理能力では高いレベルを示すものの、リアルタイムの情報検索という面ではまだ制限があります。また、FeloやGensparkなどの検索系AIツールは、情報の収集に特化している一方で、収集した情報の加工や分析という面ではPerplexity AIほどの柔軟性を現状は持ち合わせていません(例えばFeloは文字数の制約が厳しく、一定以上の複雑なプロンプトを投入することは難しい仕様です)。
もちろん生成AIの進化は著しく、各ツールの性能や特徴は日々アップデートされています。当社の見解としては、Perplexity AIを含めて特定のツールを絶対視する必要は一切なく、用途や目的に応じて適切なツールを常に見極め、選択することが重要だと考えています。
しかし、情報検索と情報処理の両立という点において、「現時点では」Perplexity AIは他の生成AIツールよりも優位な立場にいるように見えます。特にインターネット上の情報を高度なプロンプトでレベル高く処理できる能力は、他のツールには見られない特徴です。
Perplexity AIと他の生成AIツール、検索エンジンとの違いは?
これまで、いくつかの生成AIツールとの比較を通じてPerplexity AIの特徴をご紹介するとともに、Perplexity AIが利用できる具体的なシーンについても言及してまいりました。生成AIの進化はすさまじく、本コラム執筆時点(2024/11/24)でも様々な生成AIツールが世界中でリリースされています。
本コラムに登場したさまざまな生成AIツールや検索エンジンとPerplexity AIの違いを一枚の図に表したものがこちらです。横軸の情報検索力はインターネット上の情報を収集する量(網羅性)とスピードを、縦軸の情報処理力は検索結果を加工、分類、または発展させる能力を表しています。

この図から見て取れる特徴的な点として、Perplexity AIは情報検索力と情報処理力の両面でバランスの取れた性能を発揮していることが挙げられます。従来の検索エンジンと比較すると、情報検索においては同等以上の能力を持ちながら、情報処理の面で大きな優位性を示しています。
一方、ChatGPTやClaudeなどの汎用生成AIツールと比較すると、これらは情報処理能力では高いレベルを示すものの、リアルタイムの情報検索という面ではまだ制限があります。また、FeloやGensparkなどの検索系AIツールは、情報の収集に特化している一方で、収集した情報の加工や分析という面ではPerplexity AIほどの柔軟性を現状は持ち合わせていません(例えばFeloは文字数の制約が厳しく、一定以上の複雑なプロンプトを投入することは難しい仕様です)。
もちろん生成AIの進化は著しく、各ツールの性能や特徴は日々アップデートされています。当社の見解としては、Perplexity AIを含めて特定のツールを絶対視する必要は一切なく、用途や目的に応じて適切なツールを常に見極め、選択することが重要だと考えています。
しかし、情報検索と情報処理の両立という点において、「現時点では」Perplexity AIは他の生成AIツールよりも優位な立場にいるように見えます。特にインターネット上の情報を高度なプロンプトでレベル高く処理できる能力は、他のツールには見られない特徴です。
Perplexity AIを活用するためのプロンプトが知りたい!と思ったら?
Workstyle Evolutionの代表を務める生成AI活用のスペシャリスト・池田 朋弘が、社会人必修の便利すぎるAIツールを厳選紹介していく「AI仕事術シリーズ」の出版を行います!第1弾は検索エンジンと生成AIが融合した革命的AIツール・Perplexity(パープレキシティ)の日本初の入門書です。Perplexity AIの基本から高度な機能までを丁寧に解説するとともに、普段使いでは気づけない目からウロコの活用事例もたっぷり掲載します。
本コラムでご紹介した各利用シーンにおける具体的なプロンプトの作成例や、超初心者向けのPerplexity AIの使い方動画など、購読者特典も盛りだくさん!本書を手に取ることで、Perplexity AI以前には戻れない、圧倒的な成果を実感してください!

Perplexity AIを活用するためのプロンプトが知りたい!と思ったら?
Workstyle Evolutionの代表を務める生成AI活用のスペシャリスト・池田 朋弘が、社会人必修の便利すぎるAIツールを厳選紹介していく「AI仕事術シリーズ」の出版を行います!第1弾は検索エンジンと生成AIが融合した革命的AIツール・Perplexity(パープレキシティ)の日本初の入門書です。Perplexity AIの基本から高度な機能までを丁寧に解説するとともに、普段使いでは気づけない目からウロコの活用事例もたっぷり掲載します。
本コラムでご紹介した各利用シーンにおける具体的なプロンプトの作成例や、超初心者向けのPerplexity AIの使い方動画など、購読者特典も盛りだくさん!本書を手に取ることで、Perplexity AI以前には戻れない、圧倒的な成果を実感してください!


本コラムの執筆者
株式会社Workstyle Evolution 生成AIコンサルタント 兼
タレント・エンパワーメント・コンサルティング
生成AI/HRコンサルタント
池上 斉弘
東京大学文学部卒、オーストラリアGriffith Business School通信制MBA修了。東証プライム上場企業の株式会社メンバーズの事業推進部門の責任者として、事業企画・広報・営業企画などの横断領域を経験。その後執行役員に就任し、新卒採用・育成責任者として2021年4月より累計1,400名の新卒採用・受入・教育の責任者を務める。2024年7月よりWorkstyle Evolution社にジョイン。
