Mapifyとは? 情報理解に革命を起こす活用手法や他の生成AIツールとの違いを徹底解説!!
2025/01/28
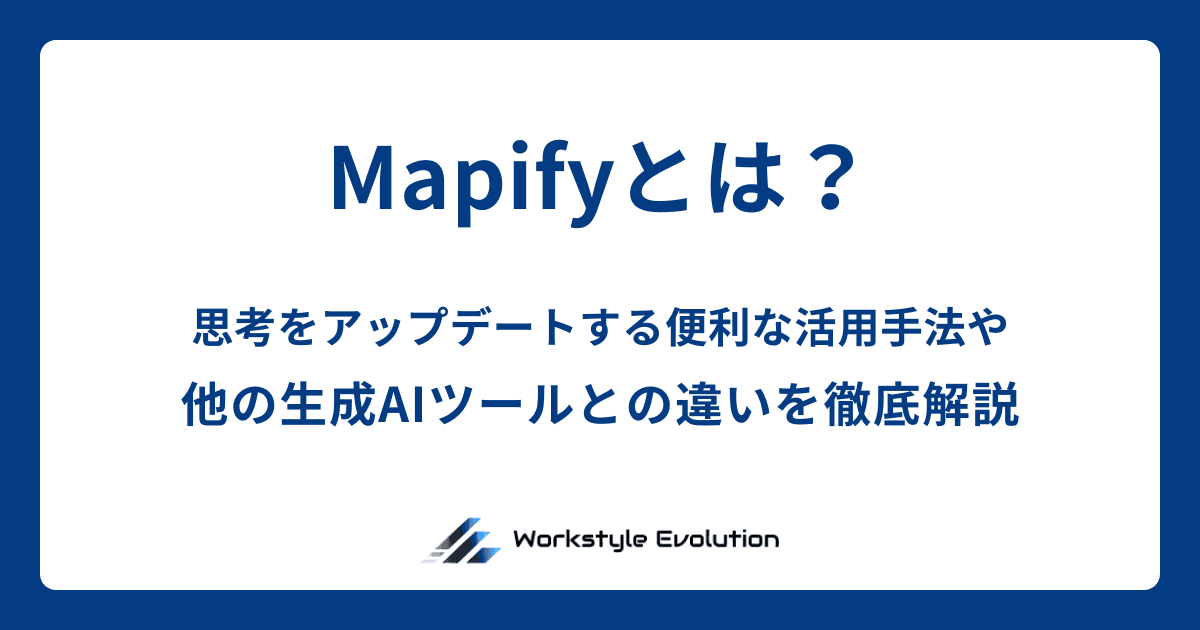
このコラムを要約すると…
Mapifyは、Xmind社が2024年に開発した「生成AI×マインドマップ」による革新的な情報ビジュアライゼーションツールです。テキスト、PDF、パワーポイント、ウェブサイト、YouTube動画、音声ファイルなど、様々な形式の情報を瞬時にマインドマップ化する機能を持ちます。
主な特徴として、GPT-4やClaude 3.5を活用した高度なAI要約機能、AIとの対話が可能なチャットボックス機能、リアルタイムウェブアクセス機能、30以上の言語への対応があります。また、生成されたマインドマップは自由にカスタマイズでき、様々な形式でエクスポート可能です。
活用シーンとしては、論文やホワイトペーパーの理解、動画内容の把握、アンケート結果の整理、なぜなぜ分析などが挙げられます。複雑な情報の全体像を可視化し、理解力を格段に高めることができます。
目次
Mapify誕生の経緯は? -情報の「海」に溺れて
現代では、インターネットやSNSの普及により、かつてないほどの情報が日々生み出され、私たちはそれらを目の当たりにしています。一説によると、現代人が1日に得る情報量は江戸時代の人々の1年分、平安時代の人々の一生分にもなるそうです。SNSの投稿やブログ、口コミサイトに加え、企業や自治体などの組織が発行するニュースやレポート、学術論文、動画の配信など、情報ソースは多岐にわたります。

情報量が増えてゆくにしたがって、私たちは「どの情報ソースに目を通せばいいのか」や「情報の中で重要なポイントはどこか」を見極めるために、膨大な労力を使うようになりました。これは、「情報過多」あるいは「インフォメーションオーバーロード」と呼ばれる現象として、1970年に社会学者のアルビン・トフラ―が「未来の衝撃」という書籍の中で提唱した概念です。膨大な情報を隅々まで読み込む時間を確保できないと、個々の内容を正しく把握できず、その情報が持つ真の意味や価値を理解できません。しかし、莫大な時間を掛けて一つひとつのソースを精読すると、タイムリーな情報の入手ができず、ビジネスなどの場面でスムーズな意思決定ができない状況にも追い込まれます。

このような背景のもと、情報を的確に整理し、スピーディな理解を推進するための工夫やアプローチは、多くのビジネスパーソンや研究者、学習者の関心事として広く受け止められてきました。その一環として、文書を素早く読むための「速読術」や、大量の文章からキーワード抽出を支援する「テキストマイニング」などの手法が注目を集めてきましたが、より直感的かつ美しく情報をビジュアライズする手法として「マインドマップ」が再注目されています。
「マインドマップ(Mind Map)」という手法は、イギリスの教育者であるトニー・ブザン(Tony Buzan)が1970年代に提唱したと言われています。中央に主題やテーマを置き、そこから分岐する形でキーワードを付けたノードを展開させ、それぞれを線や矢印でつないでいくことで、階層構造や要素同士の関連性が一目でわかるというメリットがあります。わたしたちは物事を考える際、脳内のシナプスが接続し、類似する概念や情報を「連想する」思考パターンを生み出します。マインドマップは、この脳内のメカニズムを視覚的に再現する優れた手法であり、ブレイン・ストーミングやワークショップ、研修といった組織内での学習で数多く活用されてきました。

美しいマインドマップは人間の知的生産性を効果的に向上する
従来、マインドマップは手書きやパワーポイントなどのビジネスツールにより作成されることが一般的でした。もちろん手書きにはメリットもありますが、膨大な情報をスピーディに扱いたい場面では不自由が生じることもあります。このような背景のもと、情報を自動的に整理・統合しマインドマップ化するAIツール「Mapify」が誕生しました。
Mapifyとは? -世界のすべてを「マインドマップ」に
Mapifyは、生成AIを活用して様々な形式の情報を瞬時にマインドマップへと変換する革新的な「情報ビジュアライゼーション」ツールです。2024年に登場し、ビジネスや学習、個人の思考整理など幅広い分野で活用されています。
Mapifyの最大の特徴は、テキスト、PDF、パワーポイント、ウェブサイト、SNS、YouTube、音声ファイルなど、多岐に渡る入力形式に対応している点です。この点はChatGPTやClaudeといった他の著名な生成AIツールと比較した際にも秀でています。文章、画像、音声などの情報形態に関わらず、ユーザーは複雑な情報を簡単に視覚化し、構造化されたマインドマップを短時間で入手することができます。
例えば、長文で執筆された海外の論文をPDFでアップロードするだけで、AIが内容を分析し、重要なポイントを抽出したマインドマップとして提示してくれます。また、該当のYouTube動画のURLを入力するだけで、動画の内容を要約したツリーを作成することが可能です。

Mapifyを開発したのは、香港に本拠地を置くXmind Ltd.です。Xmindは2006年に創業し、翌年には最初のプロダクトである「XMind 1.0」をリリースしました。Xmindは世界中の企業や教育機関、個人ユーザーの支持を集めたテクノロジー企業の一つとして堅調に成長し、2018年にはAsia-Pacificリージョンにおける高成長企業として英フィナンシャル・タイムス社から認定されています。これら長年にわたって培われたマインドマップの作成ノウハウと、改良の蓄積が、Xmindの大きな強みとなっています。そうした数々の実績を背景として、新たな生成AI技術を取り入れたMapifyのリリースを2024年に実現したのです。
しかし、Mapify誕生までの道のりは決して平坦といえるものではありません。XMindは「今日を革新し、明日をインスパイアする」という理念のもと、マインドマップというフレームワークを世界中に広げ、人々の思考の可視化と創造性の促進を実現したいと長年考えていました。しかし創業者 兼 CEOのBrian氏自身が「多くのユーザーは、現在のXmindが10年前に使用した製品と根本的に異なるとは感じていなかった」と語る通り、Mapify誕生以前のXmindの製品や、マインドマップという領域の進化は限定的なものでした。その意味で、生成AIという新しい技術の登場は彼らにとって大きなターニングポイントであったといえます。
XMindは2023年5月、Chatmindという創業わずか50日のAIマインドマッピングツール開発企業を買収し、生成AIによる革新的なプロダクトの創出を目指しました。従来の「マインドマップにまとめる」プロセスを人の手ではなく、AIにやらせることができれば、情報を構造化するまでのハードルを大きく下げられるとXMindは考えたのです。結果として2024年6月にChatmindがMapifyにリブランドされた際、Brian氏は「マインドマッピングの世界における大きな飛躍」を示すことができたと語っています。
人々のイノベーションや創造性を拡張するという壮大なビジョンをもつXmindは、まさに生成AIという技術を通じてその野心を再点火したばかりであり、さらなる革新が私たちにもたらされることが期待されます。
Mapifyの特徴は? -知の創造力とコラボレーションを促進
Mapifyは、AIを活用した革新的なマインドマップ生成ツールとして、多様な機能と特徴を備えています。以下に、Mapifyの主要な機能と特徴を詳しく解説します。
AIによる自動マインドマップ生成
Mapifyの中核となる機能は、AIによる自動的なマインドマップの生成です。所定の入力画面にテキスト、PDF、パワーポイント、ウェブサイト、SNS、YouTube、音声ファイルなどの情報を入力すると、AIが分析し、重要な要素を抽出して構造化されたマインドマップを自動的に作成します。この機能により、ユーザーは複雑な情報を視覚的に整理し、理解しやすい形で確認することが可能です。
高度なAI技術の活用
Mapifyの開発には、最先端のAI技術が活用されています。具体的には、OpenAI社のGPT-4oとAnthropic社のClaude 3.5モデルを採用しており、これらの高度なAIモデルにより、高品質なAI要約機能を実現しています。各社が提供する生成AIの性能は日々進化する状況にあるため、Mapifyで生成されるマインドマップの品質は今後も継続的に向上することが予想されます。
AIチャットボックス機能
ユーザーはマインドマップを作成しながら、AIチャットと対話し、生成されたマインドマップの内容について質問したり、さらに詳細な情報を求めたりすることが可能です。例えば、表示されたマインドマップに関連した特定のトピックについてより深く掘り下げたい場合や、関連する情報を探したい場合、AIチャットボックスへの質問を通じて回答を得ることができます。

AIチャットボットをマインドマップ作成時のアシスタントとして利用する
リアルタイムウェブアクセス機能
Mapifyには、インターネット上の情報を検索する機能が搭載されています。この機能により、マインドマップ作成中に所定の情報をリアルタイムで取得し、マインドマップに反映させることができます。例えば、特定のトピックに関する最新のニュースや統計データを自動的に取り込み、マインドマップを常に最新の情報に更新することが可能です。この機能は、例えば最新の業界や技術動向を踏まえたアイデア出しや、ブレイン・ストーミング等を実施する際に便利です。

ウェブ検索結果からマインドマップを作成した様子
多言語対応
Mapifyは、グローバルな利用を想定して設計されており、30以上の言語をサポートしています。この多言語対応により、言語の壁を越えて、世界中の知識にアクセスすることが可能になります。例えば、英語のコンテンツを日本語のマインドマップに変換したり、逆に日本語のコンテンツを外国語のマインドマップに変換したりすることができます。国際的なプロジェクトや多言語環境での学習など、グローバルなコラボレーションを実現する際に有用な機能です。
カスタマイズ可能なマインドマップ
Mapifyで生成されたマインドマップは、ユーザーのニーズに合わせて自由にカスタマイズすることができます。レイアウト、色彩、ノードの形状など、様々な要素を調整することが可能です。また、手動でノードを追加したり、既存のノードを編集したりすることもできます。この柔軟性により、ユーザーは自分の思考プロセスや好みに合わせてマインドマップをパーソナライズすることができます。
エクスポートと共有機能
作成したマインドマップは、様々な形式でエクスポートすることができます。画像、PDF、SVG、Markdownなど、多様なフォーマットに対応しているため、他のアプリケーションやプラットフォームで転用することが容易です。特に、Gammaなどの生成AI×プレゼンツールと組み合わせることで、高品質な資料をスピーディに作成することができます。また共有用リンクが生成できるため、Mapifyのアカウントを持っていない人とも簡単にマインドマップを共有することが可能です。
Mapifyの活用方法は? -人間の思考様式をアップデート
Mapifyは学習、分析、プレゼンテーションなど、様々な場面で活用できる強力なツールです。学習(インプット)、分析(プロセス)、プレゼン(アウトプット)それぞれの場面でMapifyがどのように人間の思考をサポートしてくれるのか、具体例を見ていきましょう。
学習における利用(インプット)
Mapifyは複雑な情報を人間の脳が受け取りやすい形で視覚的に整理し、効率的な学習をサポートすることができます。
(1)論文やホワイトペーパーの全体像把握
研究論文やホワイトペーパーは、豊富な情報と入り組んだ構成で作成されることが一般的です。そんな文書も、Mapifyを活用すれば瞬時に全体の要点を理解することが可能になります。たとえば、50ページにわたる専門的な論文をMapifyに読み込ませると、AIが自動で重要な理論や手法、成果、まとめなどを見つけ出し、体系的なマインドマップとして可視化してくれます。その結果、論文の骨格や核となるポイントが一度に把握でき、詳しく読む前に大まかな展開を理解できます。

海外の論文の主要な論点をMapifyで可視化した様子
(2)動画内容の把握
インタビューやオンライン講座、ウェビナー、プレゼンテーションなどの動画コンテンツが豊富に存在する現代において、Mapifyの動画内容把握機能は非常に有用です。
YouTubeのURLを入力するだけで、AIが動画の内容を分析し、主要なトピックや概念を抽出してマインドマップを生成します。例えば、1時間の講義動画をMapifyに入力すると、講義の構造、主要な論点、キーワードなどが視覚的に整理されたマップが作成されます。
これにより、動画を見る前に内容の概要を把握したり、視聴後に復習の際の参考資料として活用したりすることができます。

Workstyle Evolution 代表の池田のYoutube動画をマインドマップ化した様子
(3)IR資料やサステナビリティ報告書の全体像把握
企業のIR資料やサステナビリティ報告書は、投資判断に限らず、業界同行や競合分析、また法人営業を行う際にも貴重な情報リソースとなり得ます。しかしその内容は多岐にわたり複雑で、かつボリュームも大きく、内容を理解するためにはかなりの労力が必要です。
Mapifyを使用すれば、これらの文書を瞬時にマインドマップ化し、企業の経営状況や主要課題、戦略などを構造化して把握することが可能です。例えば数十ページに渡る決算報告書をMapifyに入力すると、売上高、利益、主要事業セグメント、財務状況、成長戦略、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みなどを階層的に整理してくれます。このマインドマップを通じて、対象企業の経営や事業の全体像を効率的に把握し、事業開発やマーケティング、営業活動といった各種の事業活動に活かすことができます。
分析における利用(プロセス)
Mapifyは、情報の整理や分析プロセスにおいても強力なツールとなります。
(1)アンケート結果の整理
大量のアンケート結果を効率的に整理し、洞察を得たい場面ではMapifyを活用することをオススメします。例えば、顧客満足度調査の結果をMapifyに入力すると、AIが回答を分析し、主要な満足要因や不満要因、改善提案などを階層的に整理したマインドマップを生成します。これにより、数百件のコメントや回答から重要なトレンドや共通のフィードバックを素早く識別することができます。

生成AIイベントのアンケート結果からマインドマップを作成した様子
また、自由記述回答の内容を視覚化することで、テキストマイニングのような高度な分析を行わなくても、回答者の声の全体像を把握することができます。異なるイベントのアンケート結果をマインドマップ内で見比べることで、参加者の意見や要望の差を比較することも可能です。
(2)課題の要因分析(なぜなぜ分析)
問題解決や品質改善において重要な「なぜなぜ分析」にもMapifyは効果的に活用できます。「なぜなぜ分析」とは、特定の問題や課題に対し「なぜ?」という質問を繰り返すことで、根本原因を探る分析手法です。Mapifyを使用すると、この分析プロセスを視覚的に展開し、各要因間の関連性を明確に把握することができます。
例えば、「製品の不良率が高い」という問題に対して、Mapifyを使ってなぜなぜ分析を行うと、問題から枝分かれする形で「設備の老朽化」「品質チェックの不手際」など想定される要因が展開されていきます。これらの要因に「なぜ設備が老朽化したまま放置されているのか?」「なぜ品質チェックが機能していないのか?」といった質問を重ねることで、根本原因に迫るプロセスを視覚化することができます。
この方法は、チーム全体で問題の構造を共有し、議論を深める際に有効です。なお、Mapifyのスタイル(ビジュアル)の一つには「特性要因図(フィッシュボーン)」というものがあり、組織内で品質改善運動を行う上で最も適したフレームワークのひとつであるとも言われています。
プレゼンにおける利用(アウトプット)
Mapifyのマインドマップは、効果的なプレゼンテーション資料の作成にも活用できます。
(1)スライドショー機能の利用
Mapifyには、作成したマインドマップを直接プレゼンテーションに変換する機能があります。この機能を使うと、入り組んだ情報や論点を分かりやすく伝えることができます。
例えば、新規プロジェクトの提案をする際、プロジェクトの目的、背景、実施計画、期待される効果などをマインドマップで表現し、それをそのままスライドショーへと変換してみましょう。マインドマップの階層構造がそのままプレゼンテーションの流れとなり、各ノードが個別のスライドの中に表示されます。この機能により、聴衆は情報が構成された全体像と詳細を同時に把握することができ、また話者は論理的で一貫性のある説明を行いやすくなります。

視覚的に優れたプレゼンを支えるスライドショー機能
(2)Gammaなどの他の生成AIツールへの転用
Mapifyで作成したマインドマップは、Gammaなどの他の生成AIツールと連携することで、さらに高度なプレゼンテーション資料を作成することができます。
例えば、Mapifyで作成した「データ分析におけるAIの利活用」というマインドマップをマークダウン形式でGammaに入力すると、AIがマインドマップの構造を解析し、詳細なプレゼンテーションスライドを自動的に生成します。Gammaは、適切な画像や図表、アニメーション効果などを作成することができる生成AIツールであり、もともと良質な資料を瞬時に作成できる点に強みがあります。さらに情報を事前にMapifyで整理し、構造を適切に設計したものをGammaに投入することで、より一段レベルの高い資料化を果たすことができるのです。

Mapify→Gammaでの資料作成の様子
このような生成AIツール間の連携は、プレゼンテーションだけでなく、レポートや企画書など、他のビジネス文書の作成にも応用することができます。Mapifyで整理したノードを基に、別の生成AIツールで正式な文書を生成することで、網羅的で高品質なドキュメントを効率的に作成することが可能です。
以上のように、Mapifyは人間の思考プロセスにおける各段階で強力な支援機能を提供します。様々な道具が人間の身体能力を高めるのと同様に、Mapifyを効果的に活用することは、人間の認知や思考機能を高めることにつながるのです。
Mapifyと他の生成AIツールとの違いは? -マインドマップの威力
大量の情報の整理や可視化という機能は、ChatGPTやGoogleが提供するNotebookLMといった、Mapify以外の生成AIツールでも実現可能です。これらのツールとMapifyの違いはどのような点にあるのでしょうか。
ChatGPTは自然言語で質問するとテキストベースの回答を得られる対話型のAIであり、文章の生成や要約に優れています。わかりやすい解説を提供してくれる半面、詳細な情報を求めた際には文字量が多くなりやすく、結果的に回答の全体像を把握するのが難しいことがあります。
Mapifyは、情報を階層化して視覚化された「マインドマップ」を提供することに特化しており、大量の情報から要点を抜き出した内容を「一枚の図」として理解することができます。ChatGPTの出力をそのまま読む際と異なり、Mapifyでは士の関連性や論点のレイアウトを明確にでき、内容を直感的に把握しやすくなります。

Mapifyを最大限に活用する -便利な機能
Mapifyは強力なAI搭載マインドマップツールですが、その機能を最大限に活用するためには、いくつかのヒントとコツを押さえておくことが重要です。
Chrome拡張機能
Chrome拡張機能を利用することで、Mapifyのサービス画面を開くことなく、インターネット上のあらゆるコンテンツをスムーズにマインドマップ化することができます。例えば、YouTube動画を視聴しながら「要約する」ボタンをクリックするだけで、AIが動画の内容を分析し、瞬時にマインドマップを生成します。
あるいは、専門性の高い海外の記事を読む際も、拡張機能のアイコンをクリックするだけで、内容を日本語に翻訳しながら自動で主要な論点をまとめてくれます。ちょっとこの情報について知りたいけど、時間がない…そんな悩みを抱えるユーザーにとって、Chromeの拡張機能は日々の情報収集や学習、研究活動を劇的に効率化してくれる強力なツールとなりえます。

段階的な生成オプション
Mapifyでは、マインドマップの出力スピードを「一気に」または「段階的に」選択することができます。複雑なトピックや大量の情報を扱う際には、「段階的に」オプションを選択することで、より正確でユーザーのイメージに沿ったマインドマップを作成することができます。各段階で生成された内容を人間が確認し、必要に応じて細かい修正や追加を行うことで、最終的により質の高いマインドマップを作成できます。


カスタマイズ機能の活用
生成されたマインドマップは、Mapify上で手動で編集・調整することが可能です。この機能を積極的に活用し、タスクの背景やプロジェクトの要件に合わせてマインドマップをカスタマイズしましょう。色分けやアイコンの追加、ノートの配置変更などを行うことで、ユーザーの好みや視点に合わせて、情報の重要度や関連性を明確に表現することができます。
Mapifyの将来性と発展性 -「情報」への向き合い方が変わる
Mapifyが提唱する「どんなコンテンツもAIマインドマップへ」というビジョンは、単なるツール開発の枠を超えて、情報化社会における私たちの情報への向き合い方と、人間同士のコラボレーションを革新するポテンシャルを秘めています。
今後も生成AIの技術進歩が見込まれるなか、より高精度な要約やリアルタイム翻訳、多次元的な情報解析などが実現される可能性は非常に高いです。将来的には、音声エージェント機能が追加されることで、ユーザーの指示やニーズを会話からリアルタイムで反映する機能も実装される可能性があります。あたかも人間とAI、あるいはAI同士で活発なブレイン・ストーミングやワークショップが実施される様子をMapify上で目の当たりにする未来が訪れるかもしれません。

本コラムの執筆者
株式会社Workstyle Evolution 生成AIコンサルタント 兼
タレント・エンパワーメント・コンサルティング
生成AI/HRコンサルタント
池上 斉弘
東京大学文学部卒、オーストラリアGriffith Business School通信制MBA修了。東証プライム上場企業の株式会社メンバーズの事業推進部門の責任者として、事業企画・広報・営業企画などの横断領域を経験。その後執行役員に就任し、新卒採用・育成責任者として2021年4月より累計1,400名の新卒採用・受入・教育の責任者を務める。2024年7月よりWorkstyle Evolution社にジョイン。
